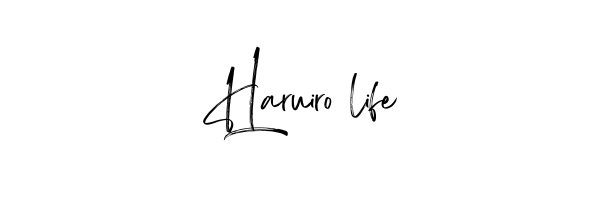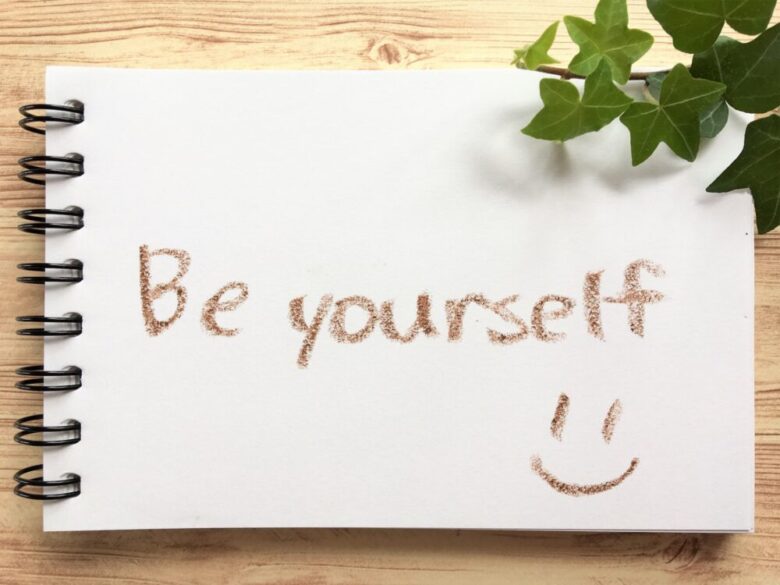あなたはイライラするとついつい物に当ったりしませんか?
よくあるのが、ついカッとなり、後でいつも自己嫌悪に陥ってしまうパターンです。
今回は、そんな「物に当たってしまう人」の心理や特徴を紹介します。
そして、当たってしまった時の対処法や、物に当たる癖を直したい、やめたいと思った時の対策についても、解説していきます。
また、恋人や両親など、身近な人が暴れると恐れを感じる瞬間もありますよね。
自分だけではなく、周囲の人が物に当たって怖いと思った時の、相手別接し方などの対応策も紹介して行きたいと思います。
時代も変わり、昔に比べ、会社内で怒るとすぐに「パワハラ」として扱われてしまう世の中になってしまいました。
本心では、怒らずに冷静に指摘するのが一番だと理解していても、中々感情をコントロールするのは大変ですよね。
そのような方のために、最近注目を集めている「アンガーマネジメント(怒りを管理する方法)」についても、紹介していきたいと思います。
物に当たりやすい人の特徴は感情表現が苦手な人?
苛立ちを我慢できない

我慢をしない事は悪い事ではないですが、社会や学校生活、家庭において、ある程度の感情コントロールする必要は大切なスキルです。
感情のコントロールが利かない人は、物に当たりやすい傾向があります。
嫌なことが起きて苛立った時、普通の人なら頭の中で、すぐに冷静になるプロセスを読み込ませるところを、短気な人はなかなか平常心を取り戻すことができません。
物事に過剰に反応し、カッとなりやすいので、条件反射的に物に当たります。
この心理的特徴を持つ人々は、日常の小さなストレスやイライラに対しても、非常に強い感情反応を示すことがあります。
そして、長期間にわたりストレスやフラストレーションが蓄積されることがあります。

これにより、人々は感情を抑えることが難しくなり、小さな刺激でも苛立ちを感じやすくなります。
また、苛立ちを我慢できない人は、適切なストレス管理スキルを持たないことがあります。
この心理的特徴を持つ人々は、自身の事や物事を適切に表現する方法やコミュニケーションスキルに課題を抱えていることがあります。
自己表現をうまく伝えられないため、苛立ちが蓄積しやすくなります。
一部の人は、自分自身や周りの環境に対する適切な認識が不足していることがあり、自分の感情やストレスの兆候を適切に理解できないため、苛立ちを我慢できなくなることがあります。
感情のコントロールが上手くできない。
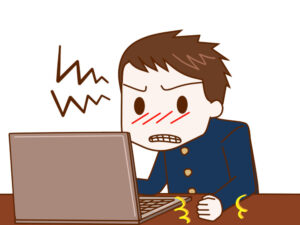
この手のタイプの人は、自分では対処できないような不測の事態に直面した時に、動揺して頭に血がのぼって物に当たってしまうという方が多いです。
特に、過去に経験したトラウマや過度のストレスが感情のコントロールに影響を与えることがあります。
感情の適切なコントロール方法や表現方法を学ぶ機会がない場合、人は感情をコントロールできないことがあり、感情教育の不足は、感情の爆発や過剰な反応をもたらす可能性があります。
そして、脳の化学的な不均衡や神経系の問題、特に精神的な健康状態の問題は、感情のコントロールに影響を与えることがあります。

精神薬などを服用している方にも、一部で感情コントロールが難しくなる場合もあります。
また、社会的な圧力や人間関係の問題、職場のストレスなど、外部からのストレス要因が感情のコントロールを難しくすることがあります。
人の性格や遺伝子によって、感情のコントロールに関する傾向が異なり、一部の人は感情をより簡単にコントロールできる一方、他の人は難しい場合があります。
ストレス発散が苦手
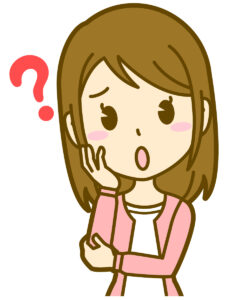
日常生活で私たちはさまざまなストレスに直面します。
しかし、中にはこのストレスをうまく発散できず、感情をコントロールすることが難しい人も存在します。

日常生活の中でさまざまなストレス要因に晒されているにもかかわらず、適切な方法でストレスを解消できずに悩んでいます…。
自分に見合った適切なストレス発散方法を、日常に取り入れる事が出来ずに、イライラした時に物に当たり発散する傾向にあります。
この工程をしっかり認識できていないと、ストレスが高まってもその原因や感じ方がわからず、対処が難しくなります。
また、そもそものコピングスキル(対処スキル)不足もストレス発散の障害となります。
ストレスをうまく処理し、コントロールするためのスキルが不足していると、ストレスが高まったときにどのように対処すればいいのかを知らないか、実践できないことがあります。
コピングスキルの向上は、ストレス発散の鍵と言えるでしょう。
社会的要因も、ストレス発散能力に影響を与えます。
虐待的な関係や高ストレス環境で育ったり、長期間にわたってこれらの状況にさらされたりすると、ストレス発散が難しくなることがあります。
環境がストレスを増幅させる場合、その影響は大きいです。
精神的な健康の問題も感情のコントロールに影響を与えます。
うつ病、不安障害、怒り管理の問題などが感情のコントロールを難しくし、暴力的な行動を引き起こす可能性があります。
精神的な健康状態は、感情の安定性に大きな影響を与えることがあります。
言葉で伝えることができない
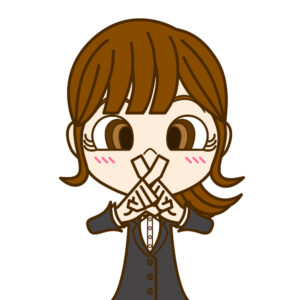
言葉で感情を伝えることが難しい人は、コミュニケーションにおいても障壁を抱えることがあります。
感情を適切に伝えられないことから、人間関係が損なわれることがあり、友人、家族、同僚とのコミュニケーションが困難になり、孤立感を感じることがあります。

感情を内にため込むことが多いため、ある時突然感情が爆発することがあります。
これは、他の人々にとって予測不可能であり、関係に緊張をもたらすことがあります。
この爆発的な感情の表出は、ストレスの一因ともなります。
言葉で感情を表現できないことが、自分自身の感情を理解するのを妨げることがあるので、感情を整理し、解釈するためのプロセスが不足しているため、自己認識にも課題が生じます。
自分の感情を理解することは、感情のコントロールにも関連しています。
この感情を、適切に表現できないことが続くと、ストレスが慢性化する可能性が高まります。
慢性的なストレスは健康に悪影響を及ぼし、身体的および精神的な健康に問題を引き起こす可能性にもなり得ます。
子どもっぽい行動をとる。

子どもっぽい行動をとる人が物に当たる理由は、決して精神年齢が低いとか、性格的にひねくれているといった事だけが、理由とは言い切れません。
感情をうまく表現できないため、成人としての適切なコミュニケーションスキルに課題が生じ、他の人との対話や関係において不適切なコミュニケーションが生じることがあります。
また、感情のコントロールにも影響が及び、感情を抑え込むことが難しいため、子どもっぽい行動が感情の発散手段として現れ、ストレスや不安を増大させる要因となることがあります。

一部の人にとっては、成熟度に未熟な部分が残っており、感情の表現が子どもっぽい行動に結びつくことがあります。
さらに、自己受容(その人が置かれている現実の状況を受け入れること)や自己評価にも影響を及ぼし、自分自身が子どもっぽい行動に対して否定的な評価を持つ場合、自尊心の低下や自己価値感の問題が浮上することがあります。
これらの理由から、子どもっぽい行動をとるタイプの人が物に当たることがあることを理解すると同時に、適切なサポートや自己成長の機会が必要であることを考慮することが重要です。
攻撃的な面がある

攻撃的な行動を持つ方の背後には、さまざまな要因が絡み合って影響を及ぼしています。
まず、タイプA行動パターン(他人とよく対立するといった行動様式)を持つ人々は、時間的な切迫感が高く、達成欲求が強いという特徴が見られます。
このパターンには攻撃性の側面も含まれ、常にストレスや焦りを感じ、他人との競争に敵意をいだきやすい傾向があります。
これらの性格特性が攻撃的な行動を促進する一因となり得ます。
また、攻撃的な傾向がある人々は、適切なストレス管理のスキルを持たないことがあります。

ストレス、不安、不満などが積み重なり、感情が爆発的に表れることがあります。
感情のコントロールとストレス管理のスキルを向上させることは、攻撃的な行動の抑制に役立つ可能性があります。
さらに、攻撃的な行動は対人関係にも深刻な影響を及ぼします。
攻撃的な態度や行動が頻繁に現れると、家族、友人、同僚との関係が損なわれ、孤立感を感じることがあります。
この孤立感が攻撃的な行動を強化する一因ともなり得ます。
自己評価と自己意識も攻撃的な行動に関与します。
攻撃的な傾向を持つ人々は、自己評価に対して敏感であり、他人の評価や意見に過度に反応することがあります。
これが攻撃的な行動の発端となることも考えられます。
また、社会的な圧力や環境の要因も攻撃的な行動に影響を与えます。
ストレスの多い環境や競争の激しい職場などでは、攻撃的な行動が増加することがあります。
これらの要因が組み合わさり、攻撃的な行動が生じることを考えると、感情管理、ストレス対処、対人関係のスキルの向上が、攻撃的な傾向の緩和や対処に役立つことが示唆されます。
気持ちに余裕が無く小心である

気持ちに余裕が無く、小心な方の物に当たる理由は、さまざまな要因が絡み合って影響を及ぼします。
まず、ストレスや不安、不満、不快感、焦りなどの感情が攻撃的な行動の原因となることがあります。
これらの感情が積み重なり、気持ちに余裕を持てなくなり、小さなことでもイライラしてしまうことがあります。
また、気持ちに余裕が無い状態では、感情をうまくコントロールできないことも挙げられます。
自分自身の感情を理解し、適切に表現することが難しく、攻撃的な行動につながることがあり、感情の正確な認識や適切な対処方法を見つけることが重要です。
さらに、一部の人は自己を守るために攻撃的な行動を取る防衛機制を持っています。

このような行動は、攻撃的に見えるかもしれませんが、本来は自分を守るために取る手段であり、攻撃性ではなく自己防衛の一環です。
ただし、この防衛機制が過度に発現することで、他人に対して攻撃的な行動が現れることがあります。
さらに、未熟な防衛機制の一つである「退行」として、受け入れがたい状況に直面したときに、現在の自分よりも幼い発達段階に戻り、困難を回避しようとすることがあります。
このような行動も攻撃的ではなく、自己保護のための防衛機制の一部ですが、感情をうまく制御できないことから攻撃的に受け取られることがあります。
以上の要因が複雑に絡み合い、攻撃的な行動が生じる一因となることを考慮すると、感情管理や防衛機制の理解、そして適切なコミュニケーションが重要であり、個人の成長と発達に関連する要素として考えられます。
自尊心が強くプライドを持っている

自尊心が強い人々が自分のプライドやイメージを守ろうとする背後には、さまざまな心理的要因が関与しています。
彼らは自分自身に高い評価を求め、他人にもその評価を示そうとすることが一般的です。
そのため、自分の欠点や失敗を認めたくないという心理が働きます。
この心理的なプロセスでは、自己評価の低下や他人からの否定的な評価を回避しようとする傾向が現れます。
自尊心やプライドが傷つけられることを恐れ、そのような状況に直面するとイライラや怒りが湧き上がることがあります。
これは、自己保身のために攻撃的な反応を示す心理的なメカニズムの一部と言えます。

攻撃的な行動は、自尊心を守ろうとする試みの一環として表れることがありますが、これが繰り返し起こると、対人関係やコミュニケーションに悪影響を及ぼすことがあります。
自己評価を高め、プライドを守ることは重要ですが、攻撃的な行動が適切なコミュニケーションや対人関係を妨げないよう、感情管理や自己認識の向上が役立つでしょう。
このようなスキルを磨くことで、自尊心を保ちつつ、より健康的な対人関係を築くことが可能となります。
アンガーマネジメントを用いて物に当たる癖を直す対処法を知ろう

アンガーマネジメントとは
怒りの感情をコントロールして生産性に結びつける研究・方法のことです。
怒りの感情とうまく付き合うための心理教育や心理トレーニングは、1970年代には既にアメリカで生まれていましたが、現代になってさらに注目を集めています。
2011年には、日本でも「アンガーマネジメント協会」という一般社団法人が誕生し、その受講者数は年々増加し、2017年には22万人を超えました。この6年で60万人も受講者数が増えたのです。
多くの人達が「自分の怒りを管理する」ことに興味を持ち、人に当たらず、スマートにコミュニケーションをとる方法を渇望しているということがわかります。
アンガーマネジメントを是非とも講習したいという方はこちらを参考にしてください。
アンガーマネジメントの具体的な方法について
怒りのメカニズムを理解し、感情的にならずに正しく対処するスキルを学ぶ。
- 怒りを感じた時に、深呼吸をすることで、感情をコントロールする。
- 怒りを感じた時に、思考を停止させることで、感情をコントロールする。
- 怒りを感じた時に、自分自身に問いかけることで、感情をコントロールする。
- 怒りを感じた時に、相手の立場を考えることで、感情をコントロールする。
自分が物に当たってしまった時の対処法
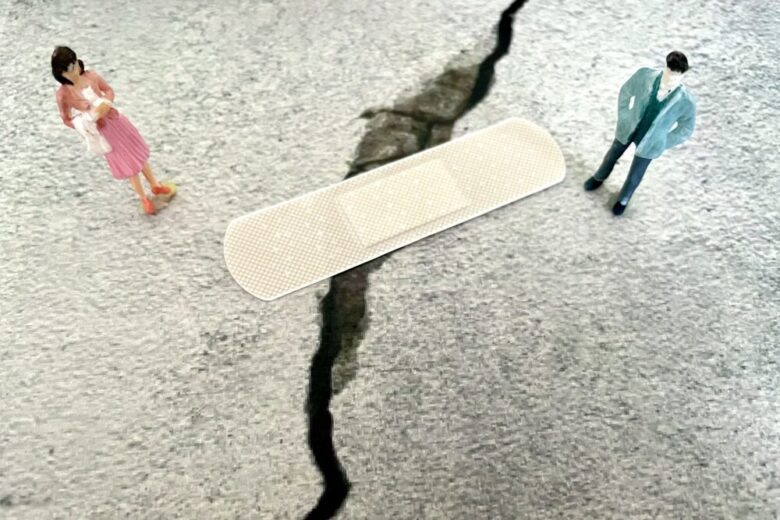
| 対処法 | 特徴 |
| タイムアウト | 感情をコントロールするために、一時的に場を離れることができる。 |
| スケールテクニック | 怒りの感情を数値化することで、冷静になることができる |
| プレイロール | 自分が尊敬する人物を演じることで、冷静になることができる |
| リフレーム | 受け取り方を変えることで、冷静になることができる |
| ポジティブフォーカス | 相手の良い部分にフォーカスすることで、冷静になることができる |
| キープメンター | 感情を定期的に吐き出すことで、怒りの感情を抑えることができる |
| アンガーログ | 怒りの感情を書き出すことで、自分自身の感情を理解することができる |
これらの方法には、メリットとデメリットが存在し、どの方法が自分、または周りの人に合うか定めた上での実地が必要になります。
自身もそうですが、周りの方とも相談し、十分に考えて実地する事をおすすめします。
タイムアウトのやり方
| 一時的に場を離れることで、感情をリセットする。 |
| 静かな場所に移動し、深呼吸をすることで、感情をコントロールする。 |
| 感情が収まるまで、時間をかけて自分自身を落ち着かせる。 |
| タイムアウト中に、自分自身の感情や考えを整理することで、感情をコントロールする。 |
上以の手順によって、一時的に場を離れることで、感情をコントロールすることができます。
| メリット | |
| 感情の冷却 | タイムアウトを取ることで、感情の高ぶりを冷静になるまで待つ時間を確保できます。冷静な状態で問題に取り組むことができ、感情的な行動や発言を抑えるのに役立ちます。 |
| 誤解や衝突の回避 | タイムアウトを利用することで、感情的な誤解や衝突を避ける機会を提供します。怒りっぽい状況で感情的に反応する代わりに、一時的に離れることで問題の悪化を防ぐことができます。 |
| 自己コントロールの向上 | タイムアウトは自己コントロールの向上に寄与します。感情を一時的に抑える訓練を受けることで、感情を適切に管理するスキルを高めることができます。 |
| デメリット | |
| 問題の一時的な解決 | タイムアウトは問題の一時的な解決策であり、根本的な問題を解決するわけではありません。感情を一時的に鎮めることはできても、問題の根本的な解決には取り組まなければなりません。 |
| 対話の中断 | タイムアウトを取ることで、対話が一時的に中断される可能性があります。これが長引くと、問題の誤解や未解決のままとなるリスクがあります。 |
| 他人との不協和 | タイムアウトを頻繁に取ることは、他人との不協和を引き起こす可能性があります。相手が感情的になった際にすぐに場を離れることは、コミュニケーションに悪影響を及ぼすことがあります。 |
| 感情の抑制 | タイムアウトは感情を一時的に抑制する方法であるため、感情を完全に解決するわけではありません。感情を放置せず、適切に処理する方法を見つけることも重要です。 |
タイムアウトは感情のコントロールに有用な方法ですが、バランスとタイミングが大切です。
適切な状況で利用することで、感情的な爆発や誤解を避け、冷静な状態で問題に取り組む機会を提供します。
スケールテクニックのやり方
| 自分の怒りの強さを10段階に分ける。 |
| 自分の怒りのレベルを数値化する。 |
| 数値化した怒りのレベルを見て、自分自身の感情を客観的に見ることができる。 |
| 数値化することで、感情をコントロールすることができる。 |
以上の手順によって、怒りの感情を数値化することで、冷静になることができます。
| メリット | |
| 感情の理解と認識 | 数値化することで、怒りの感情を客観的に評価し、それを認識するのに役立ちます。 |
| 冷静な反応 | 怒りを数値化することは、冷静な判断を下すのに役立ちます。感情を数字で表現することで、感情に振り回されずに冷静に対応できる可能性が高まります。 |
| トラッキングと改善 | 数値化した怒りの感情を記録し、トラッキングすることで、感情のパターンやトリガーを把握しやすくなり、改善の余地が見つけやすくなります。 |
| デメリット | |
| 感情の単純化 | 怒りを数値化することは、感情の複雑さを単純化する危険性があります。感情は個人によって異なり、数値だけではその深さや背後にある要因を完全に捉えられないことがあります。 |
| 感情の無視 | 数値化に過度に依存すると、感情を無視しようとする傾向が生じるかもしれません。感情は時には重要な情報を提供し、無視することは問題を悪化させる可能性があります。 |
| 数値の主観性 | 怒りの数値は主観的であり、人によって異なるかもしれません。この主観性は、他の人とのコミュニケーションにおいて混乱を招く可能性があります。 |
スケールテクニックは感情管理のツールとして役立つことがありますが、感情を数値化することは常に適切ではなく、注意が必要です。
感情の複雑さと個人差を認識しつつ、適切に活用することが大切です。
プレイロールのやり方
| 自分が尊敬する人物を選ぶ。 |
| 選んだ人物の特徴や行動をイメージする。 |
| 演じることで、自分自身を客観的に見ることができる。 |
| 自分自身をその人物になりきって演じる。 |
| 自分自身を客観的に見ることで、冷静になることができる。 |
以上の手順によって、自分が尊敬する人物を演じることで、冷静になることができます
| メリット | |
| 感情のコントロール | 尊敬する人物を演じることで、その人物の冷静さや感情のコントロールを模倣することができます。これにより、自分自身の感情をより効果的にコントロールできるでしょう。 |
| ポジティブな影響 | 尊敬する人物の特徴を模倣することで、その人物のポジティブな影響を受けることができます。彼らの価値観や行動を取り入れることで、より良い判断や行動を促進できます。 |
| 自己改善 | このアプローチは、自己成長と改善に役立ちます。尊敬する人物を演じることで、自己評価を高め、より良いバージョンの自分になる助けになります。 |
| デメリット | |
| 個人の一貫性 | 他の人物を演じることは、自分自身との一貫性を損なう可能性があります。自分自身であり続けることが難しくなり、他人に過度に依存することが問題となる可能性があります。 |
| ストレスとプレッシャー | 他人の役割を演じることは、ストレスやプレッシャーを伴うことがあります。自分にはできないと感じる場合や、他人の期待に応えるプレッシャーがかかることがあります。 |
| 適切なコンテキスト | 他人の役割を演じることは、すべての状況で適切ではありません。自分自身の感情やアイデンティティを表現する必要がある場面では、他人を演じることが適切でないことがあります。 |
| 感情の抑制 | 他人を演じることは、感情を抑制し過ぎる可能性があります。感情は時には重要な情報を提供し、完全に抑えることが適切でない場合があります。 |
プレイロールは感情管理や自己成長のツールとして有用である一方で、注意が必要です。
適切な状況で使用し、自分自身の一貫性を保ちながら、他人の特徴を活用することが大切です。
リフレームのやり方
| 受け取り方を変えることで、物事をポジティブに解釈する。 |
| 負の感情を抱いている状況を、別の視点から見ることで、冷静になることができる。 |
| 「どうしても嫌だ」と思っていることを、「どうしたらいいか」という問題解決に向けて考えることで、冷静になることができる。 |
以上の手順によって、受け取り方を変えることで、冷静になることができます。
| メリット | |
| 冷静な判断 | リフレームを用いると、感情や状況に冷静に対処できるようになります。受け取り方を変えることで、感情を抑えつつ、より冷静な判断を下すことが可能です。 |
| ストレス軽減 | ポジティブなリフレーミング(状況を肯定的に受け取る方法)を使用することで、ストレスや不安を軽減できます。状況をより前向きな視点から見ることで、感情的な負担を軽減します。 |
| 問題解決 | リフレーミングは問題解決に役立ちます。新しい視点を得ることで、問題の原因や解決策が明らかになりやすくなります。これにより、より効果的な行動計画を立てることができます。 |
| デメリット | |
| 無理なポジティブ思考 | リフレーミングを過度に行うと、現実を無視してポジティブに見ようとすることがあります。これが過度になると、問題を深刻に取り過ぎずに適切に対処することが難しくなる可能性があります。 |
| 感情の抑制 | リフレームを用いて感情を抑えすぎることがあります。感情は時には重要な情報を提供し、無視するべきではない場合もあります。 |
| 他人の感情との誤解 | 自分の受け取り方が変わったとしても、他人の感情や意図が変わるわけではありません。リフレーミングが他人の感情との誤解を生む可能性があるため、コミュニケーションに注意が必要です。 |
| 適切なタイミング | リフレーミングを適切なタイミングで行うことが重要です。感情が非常に高ぶっている場合には、すぐにリフレームを行うのが難しいことがあります。 |
リフレームは感情管理やストレス軽減に役立つ方法ですが、適切なバランスとタイミングが必要です。
感情を無視せず、現実を認識しながらポジティブな視点を持つことが大切です。
ポジティブフォーカスのやり方
| 相手の良い部分にフォーカスすることで、自分自身の感情をコントロールする。 |
| 相手の良い部分を見つけることで、自分自身を客観的に見ることができる。 |
| 相手の良い部分にフォーカスすることで、自分自身の感情をポジティブに変えることができる。 |
以上の手順によって、相手の良い部分にフォーカスすることで、冷静になることができます。
| メリット | |
| 冷静なコミュニケーション | 相手の良い部分にフォーカスすることで、冷静なコミュニケーションを維持しやすくなります。感情的な反応を抑え、対話を建設的に進めることができます。 |
| ストレス軽減 | ポジティブフォーカスは、ストレスや不安を軽減するのに役立ちます。相手の長所や良い点に注意を向けることで、感情的な負担が軽減され、ストレスが減少する可能性があります。 |
| 協力促進 | 相手に対するポジティブなアプローチは、協力や協調を促進します。相手を評価し、感謝の気持ちを示すことで、良好な関係を築く助けになります。 |
| デメリット | |
| 現実を無視 | 過度なポジティブフォーカスは、現実を無視し、問題を見過ごす可能性があります。相手の問題行動や課題を無視してしまうことが、長期的には問題を悪化させることがあります。 |
| 信頼性の問題 | 相手の良い部分に過度にフォーカスすることが、信頼性の問題を引き起こす可能性があります。感情的になりすぎず、客観的な判断を下すことが難しくなることがあります。 |
| バランスの取れない関係 | 適度な批判や指摘がない関係は、バランスを欠いてしまうことがあります。長期的な健全な関係を築くためには、問題や課題にも注意を払う必要があります。 |
| 感情の抑制 | 相手の良い部分にフォーカスしすぎることで、自分の感情を抑えすぎる可能性があります。感情を表現しないことがストレスの原因となることがあります。 |
ポジティブフォーカスは、冷静なコミュニケーションやストレス軽減に役立つ方法ですが、過度に行うことは問題を見過ごす可能性があるため、バランスを保つことが大切です。
感情を無視せず、現実的な評価を持つことが重要です。
キープメンターのやり方
| 感情を定期的に吐き出すことで、怒りの感情を抑えることができる。 |
| 静かな場所に移動し、深呼吸をすることで、感情をコントロールする。 |
| 吐き出す相手は、信頼できる人であることが望ましい。 |
| 吐き出す相手には、自分自身の感情を理解してもらえるように、自分の気持ちを正直に伝えることが大切である。 |
以上の手順によって、感情を定期的に吐き出すことで、怒りの感情を抑えることができます。
| メリット | |
| 感情の解放 | 怒りの感情を吐き出すことで、感情の圧力を解放できます。溜まった怒りを発散することで、内部の緊張が軽減され、リフレッシュされることがあります。 |
| 冷静な判断 | 怒りを感じているときに感情を吐き出すことで、冷静な判断を下しやすくなります。感情的な過剰反応を避け、問題に対処するためのクリアな思考を促進します。 |
| ストレス軽減 | 怒りを抱え続けることは、ストレスを引き起こすことがあります。感情を吐き出すことは、ストレスの軽減に寄与し、心身の健康に良い影響を与えることがあります。 |
| デメリット | |
| 環境への影響 | 怒りを感情的に吐き出すことが、周囲の環境に悪影響を及ぼすことがあります。他の人に対して攻撃的な言動や行動をとることで、関係が損なわれる可能性があります。 |
| 感情のエスカレーション | 怒りを感情的に吐き出すことが、感情のエスカレーションを引き起こすことがあります。感情を表現する過程で感情が増幅され、冷静さを保つのが難しくなることがあります。 |
| 過度な依存 | 怒りを吐き出すことに過度に依存することが、感情のコントロールを難しくする可能性があります。感情を吐き出すことが唯一のストレス対処方法となり、健康的な対処方法が欠如することがあります。 |
| 問題解決の遅延 | 怒りを吐き出すことは、感情の解放には役立つかもしれませんが、問題の根本的な解決には貢献しません。問題の解決を遅延させる可能性があります。 |
キープメンターは感情管理の一つの方法ですが、過度に感情を吐き出すことや感情的な暴力を含む行動については注意が必要です。
感情を解放することと冷静さのバランスを取ることが大切です。また、感情を吐き出す方法として適切な方法を見つけることも重要です。
アンガーログのやり方
| 怒りの感情を書き出すことで、自分自身の感情を理解することができる。 |
| 怒りの感情を書き出すために、アンガーログと呼ばれる日記をつける。 |
| アンガーログには、怒った出来事やその原因、自分自身の感情などを書き出す。 |
| アンガーログを書くことで、自分自身の感情を客観的に見ることができる。 |
| アンガーログを書くことで、自分自身の感情を理解することができる。 |
以上の手順によって、怒りの感情を書き出すことで、自分自身の感情を理解することができます。
怒りを紙に書き出すことで、感情的な圧力を解放し、ストレスを軽減できます。
感情を外に出すことで、心身のリラックスを促進します。
| メリット | |
| 感情の理解 | アンガーログを書くことで、自分の怒りの感情を深く理解できます。感情を文章にすることで、その感情の原因や背後にある要因を明確にする手助けになります。 |
| 冷静な視点 | 文字にすることで、感情を客観的に見ることができます。感情を吹き飛ばすことなく、冷静な視点から自己評価を行うことができます。 |
| ストレス軽減 | 怒りを紙に書き出すことで、感情的な圧力を解放し、ストレスを軽減できます。感情を外に出すことで、心身のリラックスを促進します。 |
| 対処策の検討 | アンガーログを書くことで、怒りに対処する方法や解決策を考える機会を提供します。感情を整理し、問題解決へのステップを明確にすることができます。 |
| デメリット | |
| 感情の強化 | 一部の人にとって、怒りを書き出すことが感情を強化することがあります。感情を文字にすることで、それにより感情が増幅されることがあるため、感情的な暴力や攻撃的な行動につながる可能性があります。 |
| プライバシーの問題 | アンガーログを誰かに見られるリスクがある場合、自由に感情を書き出すことが難しくなることがあります。プライバシーを確保できない場合、本音を書き出すのがためらわれるかもしれません。 |
| 問題の先送り | アンガーログを書くことで、怒りの感情を一時的に発散させることができますが、根本的な問題の解決には貢献しないことがあります。感情の発散と同時に、問題の根本的な解決を追求することも重要です。 |
| 依存のリスク | アンガーログを頼りすぎることで、感情管理の他の方法を見落とす可能性があります。感情を書くこと以外の方法も併用し、バランスを取ることが重要です。 |
アンガーログは怒りの感情管理に役立つ方法ですが、過度に依存せず、他の感情管理戦略と組み合わせることが大切です。
感情を理解し、建設的な対処策を見つけるための手段として活用できます
物に当たるのをやめたいけど、やめれない?周りの人ができる対処法は冷静な対応!

周りの人が物に当たってしまった時の場面に遭遇した際、すぐにできる対処法
| ・タイムアウトを提案し、一時的に場を離れることで、感情をコントロールすることができる。 相手の良い部分にフォーカスすることで、冷静になることができる。例えば、相手が優れた能力を持っていることに注目することができます。 |
| ・相手の感情を理解することで、感情をコントロールすることができる。例えば、相手がストレスを抱えていることに気づき、そのストレスを解消する方法を提案することができます。 |
| ・相手の話を聞くことで、感情をコントロールすることができる。相手が話をすることで、感情を吐き出すことができ、冷静になることができます。 |
| ・相手に対して、自分自身の感情を正直に伝えることで、感情をコントロールすることができる。自分自身の感情を伝えることで、相手が自分自身の行動を振り返ることができ、冷静になることができます。 |
物に当たってしまった人に対して、どのような言葉で声をかけるべきですか?
| 🔹「大丈夫ですか?怪我はありませんか?」と声をかけ、相手の安全を確認する。 |
| 🔹「落ち着いてください。一緒に考えましょう」と声をかけ、相手の感情を落ち着かせる。 |
| 🔹「話を聞かせてください。あなたの気持ちを理解します」と声をかけ、相手の話を聞くことで感情を吐き出す機会を与える。 |
| 🔹「私たちは一緒に解決策を見つけましょう」と声をかけ、相手と一緒に問題解決に向けて考えることができる。 |
| 🔹「あなたの感情を理解します。でも、物に当たることは危険です。もう一度考えてみましょう」と声をかけ、相手に冷静になるように促す。 |
物に当たってしまった人に対して、どのような行動をとるべきですか?
| ✅落ち着いた声で話しかけ、相手の安全を確認する。 |
| ✅相手の感情を理解し、共感する。 |
| ✅相手の話を聞き、感情を吐き出す機会を与える。 |
| ✅相手に対して、自分自身の感情を正直に伝えることで、相手が自分自身の行動を振り返ることができる。 |
| ✅相手に対して、冷静になるように促す。 |
| ✅相手に対して、怒りの感情コントロールの方法を提供する。 |
専門家への相談

物に当たってしまう行動が改善されない場合、一人で抱え込まずに専門家のサポートを受けることが非常に重要です。専門家の力を借りることで、怒りの感情と効果的に向き合い、健康的な対処法を身につけることができるからです。
専門家は問題解決の強力な味方
物に当たるという行動は、表面的な問題に見えても、その背景にはストレス、過去の経験、思考の癖など、様々な要因が複雑に絡み合っていることが少なくありません。ご自身では気づきにくいこれらの根本原因を特定し、適切なアプローチで解決へと導いてくれるのが専門家です。
たとえば、アンガーマネジメントの専門家は、怒りのメカニズムや、怒りを感じた際の具体的な対処法について体系的な知識を持っています。彼らは、感情の波を認識し、衝動的な行動に走る前に立ち止まるためのスキルや、怒りを建設的なエネルギーに変える方法を教えてくれるでしょう。ワークショップ形式で実践的な練習を取り入れたり、個別のカウンセリングを通じて、その人に合ったカスタマイズされたアドバイスを提供したりします。
心理カウンセラーは、より深く心理的な側面からサポートしてくれます。なぜ物に当たってしまうのか、その根底にある感情や思考パターンをじっくりと探り、自己理解を深める手助けをしてくれます。例えば、幼少期の経験や人間関係のパターンが現在の怒りの感情にどう影響しているのか、といったことを丁寧に紐解いていくことで、根本的な解決に繋がります。カウンセリングを通じて、自分の感情を適切に表現する方法や、他者との健全なコミュニケーションスキルを習得することも可能です。話を聞いてもらうだけでも、心が軽くなり、客観的な視点を得られることがあります。
精神科医は、怒りの感情があまりにも強く、日常生活に支障をきたしている場合や、うつ病や不安障害などの精神疾患が併存している可能性が考えられる場合に、医学的な観点から診断や治療を行います。必要に応じて薬物療法を検討することもありますが、それはあくまで症状を和らげるための一つの選択肢であり、カウンセリングと併用することでより効果を高めることが期待できます。精神科医は、心身両面からのアプローチで、症状の改善を目指します。
このように、それぞれの専門家が異なる強みを持っていますが、共通しているのは、客観的な視点と専門知識に基づき、あなたの問題解決を強力にサポートしてくれる点です。一人で悩みを抱え込むよりも、専門家の知見を借りることで、より早く、確実に状況を改善できる可能性が高まります。
どこで相談できるか
専門家への相談を考えた際に、「どこに行けばいいのか分からない」と戸惑う方もいらっしゃるかもしれません。主な相談窓口は以下の通りです。
1. 心療内科・精神科
心療内科や精神科は、心の不調が身体的な症状として現れている場合や、精神的な問題を抱えている場合に受診する医療機関です。医師による診断を受け、必要に応じて薬の処方や、カウンセリングなどの治療が受けられます。
メリット:
- 医療保険が適用される場合があるため、費用負担が比較的少ないことがあります。
- 医師による診断が受けられ、適切な治療方針が立てられます。
- 心身両面からのアプローチが可能です。
注意点:
- 待ち時間が長い場合があります。
- 医師の専門分野や治療方針は様々なので、自分に合うかどうかを見極めることが大切です。
2. カウンセリングルーム・心理相談室
民間のカウンセリングルームや、大学の心理相談室、NPO法人などが運営するカウンセリング機関です。臨床心理士や公認心理師といった専門資格を持ったカウンセラーが、じっくりと話を聞き、心理療法を通して問題解決をサポートします。
メリット:
- 予約制で待ち時間が少なく、プライバシーが守られやすい環境です。
- 話をじっくり聞いてもらい、自己理解を深めることができます。
- 薬物療法に抵抗がある方にも適しています。
注意点:
- ほとんどの場合、医療保険が適用されず、費用が比較的高めになることがあります。
- カウンセラーとの相性が重要になります。
3. 地域の相談窓口・公的機関
各自治体や保健所が提供している無料の相談窓口も有効な選択肢です。例えば、精神保健福祉センターや保健所では、心の健康に関する相談を受け付けています。また、DV防止のための相談窓口など、特定のテーマに特化した相談機関もあります。
メリット:
- 無料で利用できる場合が多いです。
- 地域の情報提供や、適切な専門機関への紹介を行ってくれることがあります。
- 匿名で相談できる場合もあります。
注意点:
- 相談できる時間や回数に制限がある場合があります。
- 専門的な治療まで踏み込むことは稀で、あくまで相談や情報提供が中心となります。
相談への第一歩を踏み出す
物に当たってしまう行動は、ご自身にとっても、周囲の方々にとっても、精神的・物理的な負担が大きいものです。この行動を改善し、より穏やかで充実した生活を送るためには、専門家のサポートをためらわずに求めることが賢明な選択です。
インターネットで地域の相談窓口を検索したり、かかりつけ医に相談して紹介を受けたりするなど、まずは情報収集から始めてみましょう。そして、一歩踏み出して専門家に相談することで、怒りの感情との健全な向き合い方を学び、より良い未来を築くことができるでしょう。
イライラして物に当たるのをやめたい:まとめ
今回は「物に当たってしまう人」の心理や特徴、その対処法をアンガーマネジメントを中心に紹介しました。
感情コントロールは得てして急に制御できなくなるものではなく、事前に学んだり改善できる事がわかりましたね。
それでも上司や先生など、自分より立場が上の人が、イライラし物に当たってしまうのを、止めるように仕向けたり、その場を改善する事はかなり難しい事だと思います。
イライラして物に当たってしまう事は、周りの人以前に本人にも様々な被害が出ます。

そうならないために、事前の環境作りが大事だと、私は思います。
少しでも実践し、改善出来るのであれば、望みは薄く感じていても実行に移すべきだと思います。
実践し失敗したとしても、なんの利にもならない事なんてありません。
物に当たってしまった本人や周りのためにも、学んだ知識は行動あってこそのものです。